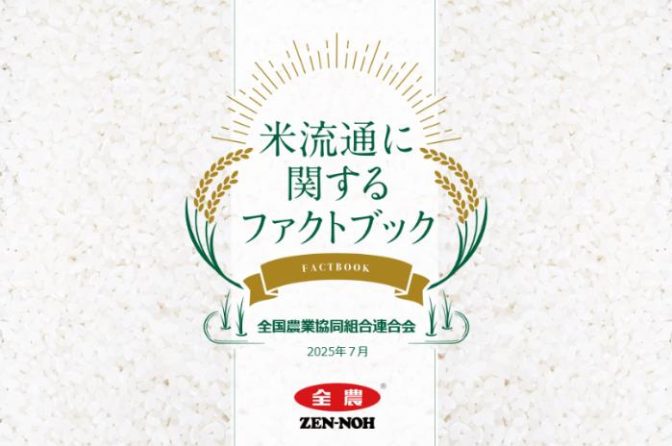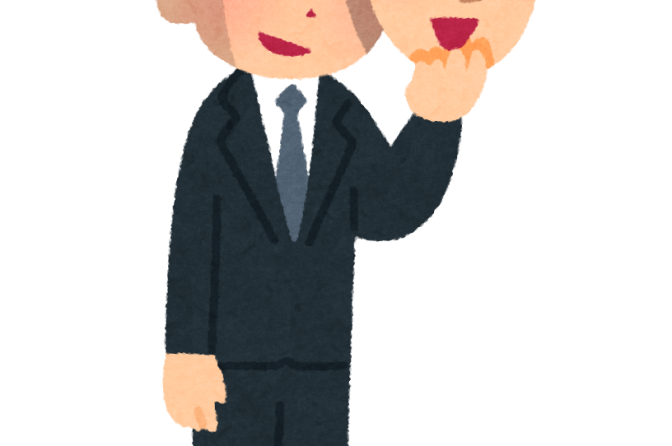ヤマタネ持続可能な稲作研究会②パネルディスカッション「明るい未来の農業を目指して」
2025/3/13/ 11:00
㈱ヤマタネ(東京都江東区、河原田岩夫社長)が開いた第2回持続可能な稲作研究会の続報。「明るい未来の農業を目指して」をテーマに、河原田社長がファシリテーターとして登壇し、生産者らとパネルディスカッションを行った。本稿では要旨を紹介する。
登壇ゲストは中森農産㈱の中森剛志代表/「e-kakashi」を手掛けるグリーン㈱の戸上崇CEO/新みやぎ農協の佐藤由一専務/秋田ふるさと農協管内の生産者・佐藤宏和氏。

生産基盤の維持・強化
〈秋田・佐藤氏〉私がなぜ利益の薄い農業をやっているのかというと、ひとえに先祖代々受け継がれてきた土地を残したいという想いからだ。稲作だけでは生活できないので、複合経営でやっているしいたけのおかげで生活費を出して(稼いで)いるような状態だ。私の集落では高齢化が進み、機械更新などの区切りで辞めてしまう人は多いが、できる限り(農地などの)受け手となってやっていきたいと思っている。
〈新みやぎ・佐藤氏〉生産者所得の向上という観点から、J-クレジット制度やさきほどの講演(もみ殻を活用したバイオマス資材)の内容など、基盤整備も含めて〝できる地域〟からどんどん取り組んでいる。ただ、管内は広域で山手から海側の気仙沼まであるので、一概に「こうすれば良い」というものが無く、新技術の導入にはコストも課題となっている。
〈中森農産・中森氏〉私は埼玉(加須市)で稲作をやっているが、ここ2年の異常気象――高温障害やカメムシの発生は凄かった。そのような問題に対しては民間でできるイノベーションを追及しているが、同時に国の政策も重要になってくる。今は一時的に相場が上がっているが、長期的な視点で、国も含めて真剣に議論していかないと立ち行かなくなるのではないか、という危機感を抱いている。
〈グリーン・戸上氏〉最近の異常気象下では、「この時期に中干しを行うぞ」「ここで防除するぞ」とこれまでの経験と勘に頼っても、成長が早くタイミングを逃し、生産性が落ちてしまう。やはり科学的根拠に基づいてデータを活用し、今の異常気象に合わせた最適な栽培管理が必要だ。
同時に、例えば一昨年は登熟期間中の気温が高かったが、これまで通りの深水管理をしたら水温が40℃を超えてしまい、逆に水を自由に使えない地域の方が品質や収量が比較的高かったなんて事例もあった。これまでの経験則を踏まえつつ新たな栽培体系を確立することが、生産の維持・強化に繋がるのではないか。
〈ヤマタネ・河原田氏〉なかなか生産人口が増えないなかで、今のお話にあったIoTなどはすごい力を発揮するだろうし、生産現場でも興味がある方は多いのではないか。
〈秋田・佐藤氏〉おっしゃる通り、生産者としてとても興味がある。しいたけ栽培で取り入れてみたところ、異常値などのデータが可視化されるので想像以上に良い。稲作でも水管理などで導入してみたいが、まだ実現していない。
〈中森農産・中森氏〉農業生産に関わる全てを変数として落とし込みたいが、件数を増やしていくと膨大な演算処理になってしまうので、一定数に絞らなくてはならない面もある。それならば作業工程を標準化したいが、その意思決定や実際に実行できる体制があるのか、という本質的な課題もある。
〈ヤマタネ・河原田氏〉生産者の年齢が70歳を超えているような現在、各地域の生産者しか持っていないノウハウをデータ化して次代に受け継ぐことができれば、農業生産体制の維持・強化にも資するのではないか。
担い手の確保
〈中森農産・中森氏〉大手企業が農業部門で求人を出すとかなりの応募があるという。労働市場、つまり若者からすると、農業界がキャリアパスには入っていない。そもそも「農業だとキャリアは積めないよね」と認識されている。しかし大手の求人には集まるわけで、私たちは「農業でも年収1,000万円を目指せますよ」というキャリアプランを提示したいと思っている。
〈ヤマタネ・河原田氏〉我々もYUIME㈱という農業人材マッチングサービスに出資しており、毎月数百人がそのサービスに登録している。ただ、実際に就農するのかは経済的な事情などでなかなか難しいかもしれない。
〈新みやぎ・佐藤氏〉農協畑を歩いてきた人間からしても、農業界は古い社会だというのが正直な思いだ。職員募集になかなか人が集まらず、若い人の声を受け入れて農協自身も変わっていかなくてはならない。担い手に目を向けると管内には農業法人も多くあるが、我々農協からすれば競合他社でもある。しかし、これからはお互いに助け合って地域を支えていかなければならない時代だ。
〈秋田・佐藤氏〉確かに農業をやりたいという若い人は意外といるが、私は今まで「米は儲からないよ」と勧めていなかった。個人的に、稲作は初期の設備投資があり、米価が見通しにくく、収入も安定しないのでハードルが高いと思っている。
〈ヤマタネ・河原田氏〉損益・収支で考えればそれなりの面積をやらなくてはならないが、そうなると今のお話の通り、初期投資がかなり膨らむ。究極的にはやはり〝儲かる農業〟を実現しないと担い手は増えていかないだろう。
儲かる農業
〈中森農産・中森氏〉そう、まさに儲かる農業だ。他業界にはリーディングカンパニーというものがあるが、農業にはない。農業は生産性が低く、高い利益率を実現できていないからだろう。当社では有機農業にも取り組んでいるが、基本的には「有機が良い」とか「悪い」ということには全く興味が無い。有機農業が儲かる農業に資するのであれば全力でノウハウを構築するし、貢献しないのであれば「なぜ利益が出ないのか」を突き詰め、その要因を減らして確実に利益が出る農業しかやらない。私はそこに持っていきたいと思っている。
〈グリーン・戸上氏〉スマート農業を進めようとしているが、これは水稲用、これは施設園芸用、これは大豆用――といった具合に、「1品目に1ソリューションを入れてくださいね」というものが多すぎる。品目は違えど同じ植物なので、データの使い回しが効くものも結構あるのだ。例えば、稲作で日照量のデータを取っていると、エリアがフラットか、などの関数があるが、それを近隣地域の大豆やシャインマスカットにも代表的な数値として適用できるケースもある。さきほど「稲作は初期投資が課題」という話があったが、一つのソリューションを上手に使いまわすことで、しっかり1年目で回収できるモデルというものを作っていきたい。
〈新みやぎ・佐藤氏〉やはり所得がしっかり残らないと担い手は減る一方だし、事業の継承もされない。今の2万円の米価でも、JA系統は「上がった」ではなく「30年前の水準に戻った」と表現している。その原因が何だったのかはここでは言及しないが、私もこれまでの米価はあまりにも下がり過ぎていたと思っている。食堂でお代わり無料が当たり前なのは米くらいなものだが、それは米の価格が安かったからに他ならない。しかし、米価が2万円になったことで、担い手の所得という観点から少し再生産に向けて光が見えてきた。
〈ヤマタネ・河原田氏〉話は変わるが外国産米について少しだけ。今は台湾産米などが店頭で比較的安価で売られ、その安さから買い求める人も少なくないが、一方で国産米を買う人も多い。これは生産者が築き上げてきた安全・安心で美味しいという信頼を求める消費者がいるということだ。野菜や果樹の世界では輸入品と国産が並ぶことは特段珍しくないが、米の世界でもそうしたことが起き始めたのは、各種シンクタンクが示している「2030年前後には米の需給バランスが逆転する」という推計を再認識するきっかけにも繋がるのではないか。現在の急激な米価上昇によって混乱が生じている一方、今まで生産者の皆さんは本当に苦労してこられたので、今後は適正価格が安定的に維持されていくのが理想だと思っている。
明るい未来の農業を目指して
〈秋田・佐藤氏〉後進を育成し、地域を盛り上げ、農業生産を効率化させることを目指していきたい。
〈新みやぎ・佐藤氏〉東北、特に宮城は水田農業がベースとなって、園芸や畜産がある構図だ。その意味では、先端技術などを積極的に取り入れながら、水田を中心とした稲作経営を前向きに取り組んでいくことが、宮城にとって明るい未来の農業に繋がると確信している。
〈グリーン・戸上氏〉日本の栽培技術・品質はすごく高い。その栽培ノウハウを科学的な根拠と合わせてサービスとして海外に販売すれば、日本の生産者が積み上げてきた経験をマネタイズできるのではないかと考えている。
そして地域の未来を考えると、次世代にどう繋ぐかも重要だ。例えば福岡県久山町の小学校に田んぼのe-kakashiのデータを表示している。現在どれくらいのCO2を吸収して脱炭素に貢献しているのか、この条件だとカメムシが発生しそう、病気が発生しそう――などを毎日更新している。すると、子どもたちが「米作りはすごいことをやっているんだ!」と理解して、下校中に会った農家に「病気が発生しそうですけど大丈夫ですか」と声をかけたりすることがある。こうした地域ぐるみでの取り組みも明るい未来の農業に繋がっていくのではないか。
〈中森農産・中森氏〉まず、政治が責任を果たすこと、そして民間がイノベーションを興すことが必要だ。米作りは食料安全保障に関わることだが、価格支持政策を大きく変える必要があるだろう。アメリカのように、粗利を補償することで再生産が出来るように国が担保しなければ、生産能力が落ち、誰も農業をやらなくなってしまう。そこは政治が責任を取ってやるべきだ。
民間がやるべきイノベーションの方向性としては、できる限り経費を削減し、単価を上げる取り組みを丁寧に進めなければならない。EUのマーケットでは有機米が1㎏6,000円で売られており、こういったプレミアムな市場を押さえる必要がある。日本は急峻な土地柄なので、規模の経済では欧米に太刀打ちすることが不可能だ。
〈ヤマタネ・河原田氏〉明るい未来の農業に向けてさまざまなご議論をいただきました。本当に農業は日本国民の食を支える重要な産業ですから、次世代が儲かる農業を実現できる仕組み――我々もその仕組みづくりに取り組んでいきたい。